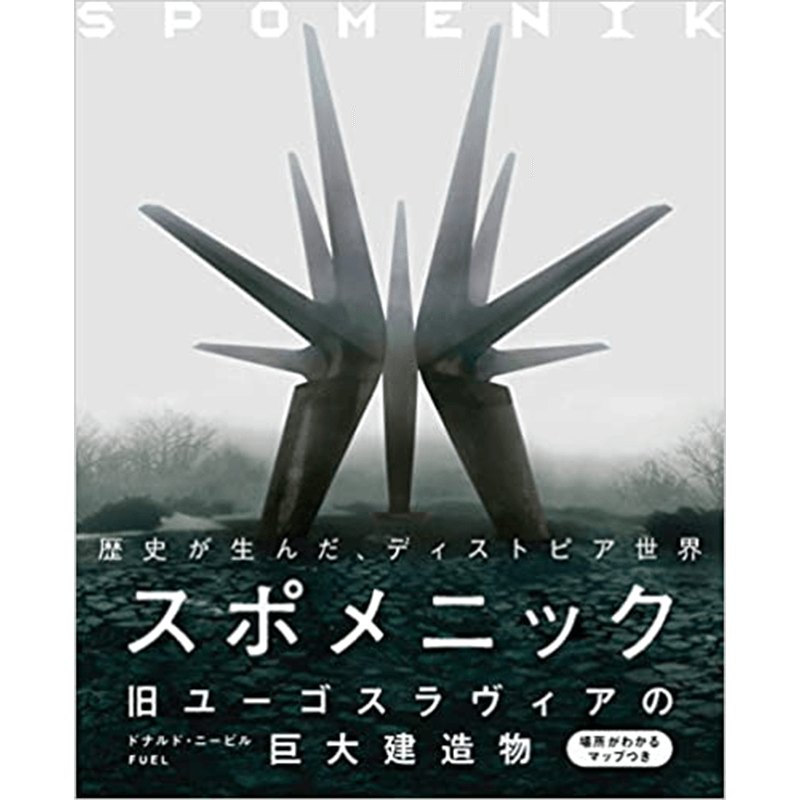スポメニック(セルビア・クロアチア語: Spomenik、「記念碑、モニュメント」の意)は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国政府によって1950年代から1980年代初頭までに当時のユーゴスラビア全土の様々な場所に建設された第二次世界大戦のモニュメント(戦争記念施設)もしくは慰霊碑の総称である。正式名称はユーゴスラビア人民解放戦争記念碑(セルビア・クロアチア語: Spomenici Narodnooslobodilačke borbe / Споменици Народноослободилачке борбе)。
他国の戦争記念碑や慰霊碑とは一線を画した、シュルレアリスムを彷彿とさせる極めて前衛的かつ未来的な形状をしているものが多いことで知られる(デザイン、歴史の項を参照)。
概要
第二次世界大戦の最中、ユーゴスラビアはナチス・ドイツを始めとした枢軸勢力による侵攻を受け、共産主義勢力であるパルチザンがこれに抵抗したことで苛烈な戦闘が勃発した。更に多民族国家であったユーゴスラビアの複数の民族がナチス・ドイツに触発される形で過激な民族統一主義団体を組織し、互いに異なる民族への大量虐殺(ジェノサイド)を行うなど、最終的にパルチザンの勝利とユーゴスラビアの再独立をもたらした戦争は数多くの惨禍を引き起こしたのちに終結した。
スポメニックの目的は、そうした枢軸勢力によって引き起こされた大量虐殺や民族浄化の犠牲となった市民を弔い、ファシズムに対し勇敢に戦い勝利したパルチザンの兵士を讃え、共産主義革命によって成し得たユーゴスラビアの独立と、かつて対立していた民族間の融和と団結を象徴する愛国的シンボルをユーゴスラビアに創ることであった。
戦時中にパルチザンを率い、後にユーゴスラビアの終身大統領となったヨシップ・ブロズ・チトーの指示により、国家プロジェクトとしてユーゴスラビア全土に2万から4万ものスポメニックが建設された。しかしその多くが1991年のユーゴスラビア崩壊と同時に勃発したユーゴスラビア紛争を経て破壊・解体されるか紛争の影響で廃墟と化し、建設時の形状を保ったまま現存しているものは全体のごく一部である。
スポメニックの材質は主に鉄筋コンクリートだが、アルミニウムやステンレス鋼などの金属で出来たものも存在する。2000年代以降、金属製のスポメニックは金属の価値に目をつけた窃盗の対象になることが多くなり、特にペトロヴァ・ゴーラやゲヴゲリヤのスポメニックはほとんど鉄の骨組みだけが残っているほど損壊が激しい。
デザイン
一口にスポメニックと言ってもそのデザインや大きさは様々であるが、スポメニックの多くは戦争記念碑としてはユニークで型破りなフォルムを持っており、その異様な形状から現在でも諸外国からの研究の対象となっているほど人々の関心を寄せる存在となっている。
ユーゴスラビアは建国当初こそソビエト連邦の社会主義リアリズムを唯一の芸術表現手段として許容していたが、ユーゴスラビアの外交政策の転換に伴い、徐々に社会主義リアリズムから逸脱した独自の文化を形成し始め、1960年代には社会主義国でありながら西側諸国の芸術運動である抽象表現主義を始めとしたモダニズムが広く見られるほど表現の自由に寛容な国家となっていた。スポメニックはユーゴスラビアの建築物の中でもモダニズムの影響が特に顕著に表れており、建築家の他、彫刻家などの美術方面の人物がデザイナーとして起用されるなど、戦争記念施設でありながらパブリックアートの様相を呈している点も特筆に値する。
こうした芸術運動がユーゴスラビアで受け入れられた要因として、モダニズムがユーゴスラビア政府にとって以下の点で都合が良いと判断されたことであった。
- 建国直後の親ソ路線からの脱却と独自の文化やアイデンティティの形成を象徴するのに適していた為
- 画題や表現に厳格な規制が設けられている社会主義リアリズムよりも、革命がもたらす未来的なビジョンをより直感的に体現しやすかった為
- 半ば民族紛争と化していた戦争を直接表現しない(抽象的な表現にとどめる)ことで、戦争の遺恨や民族間の緊張の再燃を抑える為
また、デザインの選考プロセスは(一部の例外を除き)殆どが公募展やコンペティションを通じた民主的な形式で行われ、政府による検閲も最小限だったことで多数の芸術家が自由に参加できた他、ユーゴスラビアには厳しい渡航制限がなく、国内の芸術家は西側諸国に渡って現代美術を制限なく学ぶことが可能であった為に芸術家のレベルが高く、個々の芸術的個性が生きたクリエイティブかつ多彩なアイデアがコンペティションを通じて多く競われた。それらの要因がスポメニックの形状を独創的なものに際立たせたと考察されている。
論争
だが、これらの抽象的なデザインに異議を唱える声は当時から少なからず存在した。論争を呼んだスポメニックの代表的な例として、デザイナーのヨルダン・グラブル(Jordan Grabul)とイスクラ・グラブル(Iskra Grabul)夫妻が手がけた北マケドニアのクルシェヴォにある『イリンデン(Ilinden)』がある。
これは内部マケドニア革命組織によるオスマン帝国に対する武装抵抗の大きな転機となったイリンデン蜂起を記念する重要な記念碑として建設の計画が進められていたが、コンペティションに勝利したグラブル夫妻が提示した草案に描かれたスポメニックの形状は、モーニングスターを模った放射状の突起がついた球体という極めて特異かつ非常に抽象的なデザインであり、更にスポメニック内部に作られるイリンデン蜂起の戦闘と同地の解放などを描いたレリーフも単なる図形の集合体にしか見えないほど非常に抽象化されていた。グラブル夫妻はこれらの要素を巡り、より具象化されたデザインを要求するユーゴスラビア政府の委員会と激しく対立した。その後の政府の譲歩によりグラブル夫妻の草案に沿う形で最終デザインが確定するも、実際に完成するまでは市民などから多くの否定的な意見が寄せられていた。
もう一つの例として、建築家のボグダン・ボグダノヴィッチ(Bogdan Bogdanović)が設計し、クロアチアのヤセノヴァツに建築された『石の花(Kameni cvijet)』がある。同地は後述するウスタシャによる大量虐殺が行われたヤセノヴァツ強制収容所の存在で悪名高く、戦時中に幾度となく発生したクロアチア人とセルビア人の深い対立とジェノサイドの遺恨を最も象徴する場所となっていた。やがてこの地に記念碑が建てられることになったが、戦争を想起させるデザインを嫌ったボグダノヴィッチは単なるハスの花を模ったシンプルなデザインの記念碑を提案し、これがチトーに気に入られた事でボグダノヴィッチのデザインが採用され、1966年に建設された。しかし、この虐殺の慰霊目的としては抽象的すぎるデザインが物議を醸し、政府関係者からの顰蹙を買った他、セルビア人の民族主義者などから「ファシストのクロアチア人がセルビア人やユダヤ人に対して起こした虐殺を直接的に表現せず、現実を暈し、犠牲者を侮辱している」といった苦情がボグダノヴィッチの元に多く寄せられ、更には脅迫や殺人予告まで送られてくる事態に発展した。
なお、スポメニックの建設を指示したチトー自身は現代美術に不快感を示す発言を度々しており、1963年には「(抽象芸術は)我々の社会主義倫理とは相容れない『受け入れがたい外国の移植物 ("unacceptable foreign implant")』であり、我々を革命の道から脱線させようとしている」と批判したこともあるが、そうした現代美術への検閲行為そのものは前述の通りあまり行われなかった。
歴史
背景
第二次世界大戦中、ユーゴスラビア王国は1941年4月に発生したナチス・ドイツによるユーゴスラビア侵攻によって解体され、ナチス・ドイツや傀儡国家のクロアチア独立国及びセルビア救国政府といった枢軸勢力の占領下に置かれていた。そうした枢軸勢力による支配からユーゴスラビアの領土を解放するべく同年6月にシサクで組織されたヨシップ・ブロズ・チトー率いるパルチザンが武力抵抗を起こし、各地でゲリラ戦を展開して占領下の村落を解放し、勢力を増やしていった。
ドイツ軍はパルチザンの武力抵抗への報復として、ナチス・ドイツが劣等人種とみなしたセルビア人の一般市民をドイツ兵1人の死亡につき100人、ドイツ兵1人の負傷につき50人殺害するという異常な方針をとり、各地で一般市民への無差別処刑を行なった(クラグイェヴァツの虐殺など)。更に過激な民族統一主義を掲げるクロアチア独立国のウスタシャやセルビア人組織のチェトニックなどはこれを利用し、それぞれ敵対する民族(ウスタシャはセルビア人やロマ人、チェトニックはクロアチア人やムスリム人)に対するジェノサイドを起こし、特に「バルカンのアウシュヴィッツ」と悪名高いウスタシャのヤセノヴァツ強制収容所ではセルビア人とユダヤ人を中心におよそ8万人から10万人もの一般市民を凄惨な方法で次々と虐殺していった。
一般市民も含めて100万人から170万人近くとも言われる凄まじい犠牲者を出し、スティエスカの戦い(黒作戦)などで一時は壊滅の危機に立たされながらもパルチザンは果敢に枢軸側との苛烈な戦争を戦い抜き、1945年4月のナチス・ドイツの降伏によりほぼ自力でユーゴスラビア全土の解放を成し遂げる形で戦争は終結し、同年11月にユーゴスラビア社会主義連邦共和国の成立が宣言された。
計画と建設
第二次世界大戦の終戦から間も無く、ユーゴスラビアの大統領となったヨシップ・ブロズ・チトーはナチス・ドイツ占領下で発生した残忍な大量虐殺の犠牲者を記憶し、パルチザンの活躍とファシズムに対する正義の勝利を讃える記念碑を、激戦地や虐殺の現場を中心とした全国各地に建設するよう指示を出した。これは社会主義の原則によって統治される階級や民族主義による差別の無い、まさにユーゴスラビアのスローガンである『兄弟愛と統一』を体現したユートピア的統一国家の建設という大統領の野心的な計画の一部であり、尚且つユーゴスラビア市民に対する思想教育やプロパガンダの一環でもあった。
1950年代前半までの初期のスポメニックは兵士や労働者の銅像といった具象化された伝統的なデザインのものが中心であったが、これは建国直後のソ連との蜜月関係が影響しており、ソ連の社会主義リアリズムに忠実に従っていた為であった。
しかし、その後ユーゴスラビアがソ連追従政策を翻し、非同盟運動及び独自の自主管理社会主義へと転換したことからソ連との関係が悪化し、ユーゴスラビア共産主義者同盟のコミンフォルムからの追放により完全な決別状態となった。そうした背景から「陳腐な」社会主義リアリズムを捨て、ユーゴスラビアの「革命」や「未来」などの概念を直感的に体現できるより適切な表現方法を探る必要に迫られた。そこでユーゴスラビア政府はマーシャル・プランなどで関係の修復が進んでいたアメリカを始めとした西側諸国で流行していた抽象表現主義を中心としたモダニズム芸術運動に目を付け、1950年代後半頃からモダニズムやミニマリズムに基づいた造形スタイルをスポメニックに取り入れ始めた。
記念碑のデザイナーとしてドゥシャン・ジャモニャやヴォイン・バキッチ(Vojin Bakić)、ミオドラグ・ジヴコヴィッチ(Miodrag Živković)、ボグダン・ボグダノヴィッチ(Bogdan Bogdanović)などの著名な彫刻家や建築家が多数参加し、こうして戦争記念碑としては極めて独特な形状をした記念碑が次々と建てられていった。
その数は1960年代までに冷蔵庫程度の小型なものから15階建ての高層ビル並みに巨大なものまで約14,000ほど建てられたとされ、1990年頃までには40,000を超えていたとする文献もある。これは戦争記念施設としては他のヨーロッパ諸国の中でも際立って多く、スポメニックがいかに大規模な国家プロジェクトだったのかが垣間見える。中でも数十あるとされる巨大なスポメニックの周りには自然公園(ランド・アート)や戦争の悲惨さを伝える博物館や資料館、無名戦士の墓やイベントスペースなどが整備され、1970年代には多くの観光客が訪れる人気スポットとなった。
紛争による破壊
しかし、1980年のチトーの死去によって厳しく抑圧されてきた民族主義が再び台頭し始めたことにより、第二次世界大戦時のウスタシャやチェトニックによる虐殺の遺恨が再燃し、民族間の対立・緊張が高まっていった。そして民族融和と団結の象徴になっているスポメニックの存在意義は段々と薄れていき、1985年を最後に新規の建設は行われなくなった。
1980年代後半のユーゴスラビアは集団指導体制への移行後に生じた各共和国間の不和の拡大に伴う国内政情や経済の不安定化と通貨ディナールの暴落、そして政府によって隠蔽されてきた戦時中にパルチザンが起こした虐殺の数々やゴリ・オトク島の強制収容所で行われてきた反体制派への残忍な粛清が公になるなど、建国時から抱えてきた諸問題が一気に顕在化したことに加え、同時期に周辺の社会主義国で巻き起こっていた東欧革命の煽りをも受け、国民の愛国心が薄れるばかりかユーゴスラビアへの不満や反発があちこちで噴出する事態に陥っていた。それに伴い国民のスポメニックに対する意識も「民族のアイデンティティを抑圧してきた社会主義がもたらした負の遺産」というものへと変化していった。
そしてユーゴスラビアは1991年に構成国の相次ぐ独立により崩壊し、その直後に勃発したユーゴスラビア紛争により再び激しい戦火に晒されることになった。その紛争の最中、戦闘による攻撃の標的にされる、住民の移動に伴う都市の荒廃によって廃墟と化す、資材捻出のために解体されるなどして多くのスポメニックが著しく損傷するか完全に破壊された。更に紛争終結後も急進的な民族主義者や反共主義者らによる破壊・落書きなどのヴァンダリズムや地元当局による解体・撤去が相次ぎ、それによってかつて2万〜4万とも言われたスポメニックは大幅に数を減らし、紛争によるスポメニックに関する記録の散逸によって詳細な現存数は現在でも不明となっている。
現在
第二次世界大戦の激戦地や虐殺の現場に建てられているスポメニックの特性上、その多くは都市部から遠く離れた場所に存在しており、場合によっては山の山頂や森の奥深くに佇んでいる例もある。そうした元々のアクセスの悪さに加えて、紛争に伴うアクセスの遮断や人口減、スポメニックに関する情報の散逸、前述のような政治的事情や地元当局・住民の無関心などによって現在でもほとんどが荒廃したまま放置され、保存に向けた動きも目処が立っていないのが実情である。
だが2010年代に入り、スポメニックの特徴的な形状がインターネットで話題に上るなどして国外からの関心を集めるようになり、スポメニックに対する研究が諸外国から行われるようになったほか、スポメニック巡りを目的とした観光客も増加している。国内でもユーゴノスタルギヤなどからスポメニックが持つ本来の意味の再評価が行われており、スポメニックやその跡地でかつて祀られた戦没者を弔うセレモニーや様々な催し物を開催したり、地域再興の目玉として比較的損傷の少ないスポメニックや周辺の観光ルートを整備したり、失われたスポメニックを復刻させる動きも少しづつだが広がっている。
また、ユーゴスラビア紛争の犠牲者を弔う新たなスポメニックの建設も行われており、有名なものとしては1991年8月9日にフルヴァツカ・コスタイニツァ近郊でセルビア人スナイパーに殺害された写真家のゴルダン・レデラー氏を追悼する為に2015年に彼の殺害現場に建設された、割れたカメラのレンズを模ったスポメニックがある。
ギャラリー
セルビア・コソボ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
クロアチア
北マケドニア
スポメニックが登場する作品
書籍
- ドナルド・ニービル 著『スポメニック 旧ユーゴスラヴィアの巨大建造物 (Spomenik Monument Database)』- グラフィック社
- 星野藍 著『旧共産遺産』- 東京キララ社
映画
- 最後にして最初の人類 - ヨハン・ヨハンソン監督による2020年の同名小説の映画化作品。映像の全シーンが各地のスポメニックと周辺の風景を映し出したフィルム映像のみで構成されている。
- すべて、至るところにある - リム・カーワイ監督による2024年の映画作品。作中の随所に映るスポメニックがテーマとなっている。
脚注
注釈
出典
関連項目
- チトー主義
- 彫刻
- パブリックアート
- ランド・アート
- レトロフューチャー
外部リンク
- Spomenik Database (英語)